2025年11月、大日本猟友会が警察官と自衛隊によるクマ駆除への参入に明確な反対を表明しました。
この反対表明に対して「縄張り意識では?」という声も上がっていますが、実際のところはどうなのでしょうか?
今回は、大日本猟友会が反対する本当の理由と、その背景にある深刻な問題について詳しく解説していきます。
大日本猟友会が反対する理由は縄張り意識?

2025年11月5日、大日本猟友会の佐々木洋平会長(83)が自民党のクマ被害対策プロジェクトチームの会合で、警察官と自衛隊によるクマ駆除に反対の立場を示しました。
一部では「縄張り意識による反対では?」という見方もありますが、実際には専門性と安全性への深刻な懸念から来る反対意見なのです。
大日本猟友会は全国で約10万人の会員を擁し、2024年には約9,100頭のクマを捕獲、シカやイノシシは年間100万頭以上を捕獲している実績があります。
この長年の経験と実績を持つ専門家集団だからこそ、付け焼き刃的な対策では安全性が確保できないと主張しているのです。
大日本猟友会が警察と自衛隊の参入を拒む3つの正当な理由

大日本猟友会が反対する理由は、大きく分けて3つあります。
1. 警察官の経験不足による危険性
佐々木会長は「クマは人を見ると向かってきて、非常に危険。知識も経験も少ない警察官が、一定の研修や訓練を受けただけで緊迫した現場で『緊急銃猟』ができるとは非常に疑問」と指摘しています。
クマ駆除は命に関わる極めて危険な作業であり、短期間の訓練だけでは対応できないという現実的な懸念です。
2. 自衛隊の本来任務への影響
「緊迫した国際情勢のなか、国防を担う自衛隊がクマ対策で箱わなの設置といった後方支援に出動することにも反対」という立場を表明しました。
これは自衛隊の本来の任務である国防への影響を懸念しての反対です。
3. 法的責任と現場体制の不備
大日本猟友会は、改正鳥獣保護管理法施行後も多くの市町村で対応マニュアルが未整備であることや、緊急銃猟で事故が起きた場合の捕獲者の責任が不明確であることを問題視しています。
また、危険な作業に対する報酬が「専門職待遇」として統一されていない待遇の問題も指摘しています。
大日本猟友会が政府に要望する4項目と今後の展望
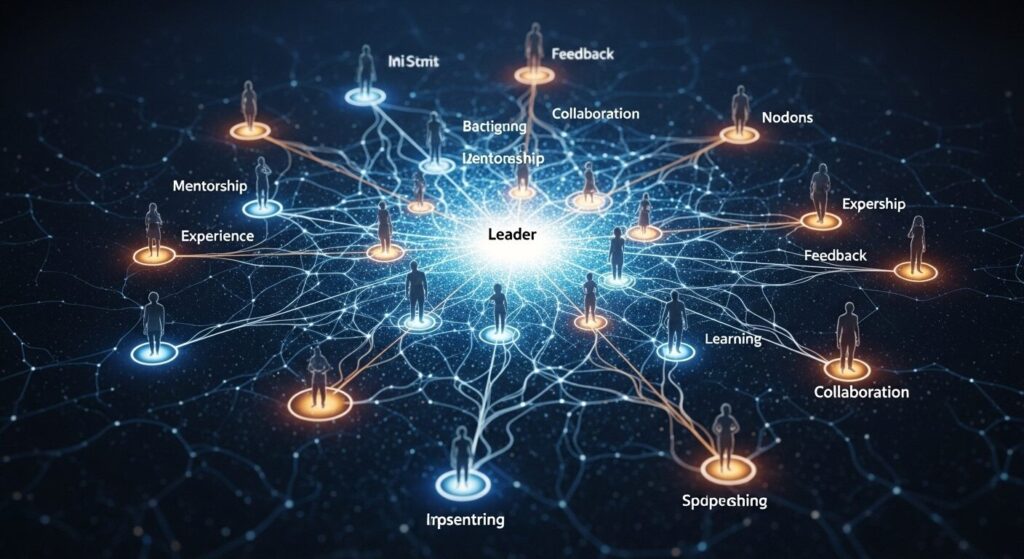
大日本猟友会は政府に対して、以下の4項目を要望しています。
1. 緊急銃猟の実態検証と担い手育成の早急な検討
現場の実態を正確に把握し、長期的な視点での担い手育成が必要だと訴えています。
2. 事故時の法改正と補償制度の確立
万が一の事故に備えた法整備と補償制度の確立を求めています。
3. 捕獲者への「専門職待遇」の統一
危険な作業に見合った適切な報酬体系の確立を要望しています。
4. 適正な個体数管理と狩猟者育成のための十分な予算確保
根本的な解決のためには、適正な個体数管理と次世代の狩猟者育成が不可欠だと主張しています。
これらの要望は、単なる反対のための反対ではなく、持続可能なクマ対策を実現するための建設的な提案と言えるでしょう。
まとめ
大日本猟友会が反対する理由は、単なる縄張り意識ではなく、専門性と安全性への深刻な懸念、そして自衛隊の本来任務への影響を考慮した正当なものでした。
警察官や自衛隊の参入は一見すると即効性のある対策に見えますが、長年の経験と専門知識が必要なクマ駆除の現場では、付け焼き刃的な対策では安全性が確保できないという現実があります。
今後は大日本猟友会が提案する4項目の要望を踏まえた、持続可能で安全なクマ対策の確立が求められています。
クマ被害対策は喫緊の課題ですが、だからこそ専門家の意見に耳を傾け、長期的な視点での解決策を模索することが重要なのではないでしょうか。
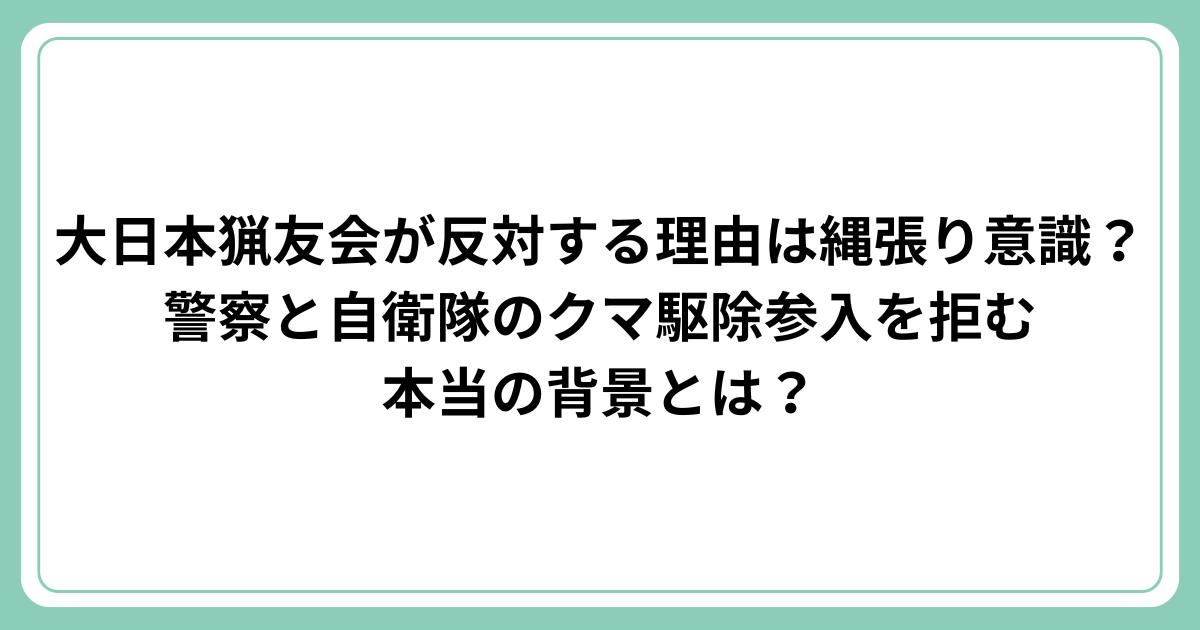
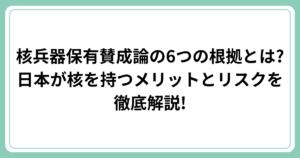
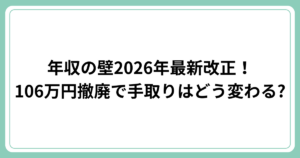
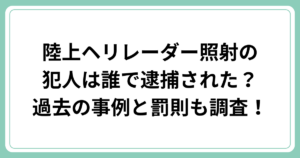
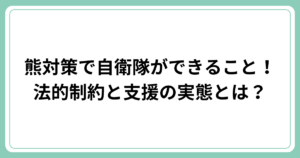
コメント